
導入:あなたの会社のSaaSは「時代遅れ」になっていませんか?
「SaaSの時代は終わった」。
もし、あなたがこの言葉を耳にしたとしたら、どう感じるでしょうか?
グローバルビジネスの最前線で働く私たちにとって、SaaS(Software as a Service)はもはや空気のような存在です。経費精算、顧客管理、プロジェクト管理…。国境を越えた業務を円滑に進める上で、SaaSは不可欠なインフラであり続けてきました。
しかし、2024年末にMicrosoftのサティア・ナデラCEOが発したとされる「SaaSのあり方は変わる」という警鐘をきっかけに、「SaaS is Dead」論が世界中で議論を呼んでいます。特にAIエージェントの急速な進化は、従来のSaaSモデルの存在意義を根底から揺るがし始めています。
駐在員として、あるいはグローバルビジネスに携わる中で、新しいツール導入の判断に迷っていませんか?「このSaaSに投資して本当に大丈夫だろうか?」という不安は、私たち子持ちのビジネスパーソンが抱える「子供の進路」や「海外生活への不安」と同じくらい、将来のキャリアと資産形成に直結する重要な課題です。
本記事では、この「SaaS 時代 終わり」論の真意を、客観的かつ論理的に解説します。そして、AI時代に生き残るためのSaaS活用戦略と、グローバルビジネスにおけるDXのヒントを提示します。
結論から申し上げましょう。SaaSは終わったのではなく、「進化」したのです。
この記事を読み終える頃には、あなたの会社のSaaSポートフォリオを見直すための明確な戦略が見えているはずです。
この記事でわかること
- 「SaaS is Dead」論が生まれた背景と、その真の論点
- グローバルビジネスにおけるSaaSの限界と、駐在員が直面する課題
- SaaSがAIと共存し、進化する具体的な方向性
- AI時代に選ぶべき「次世代SaaS」の条件と戦略
1. なぜ「SaaS is Dead」論が生まれたのか?【市場の成熟とAIの衝撃】
1-1. SaaS黄金時代の終焉:市場の飽和とCAC高騰
SaaS市場は、2000年代から驚異的な成長を遂げてきました。しかし、主要な業務領域(CRM、SFA、HRMなど)では市場が成熟し、競争が激化しています [1]。
この結果、SaaS企業は以下の課題に直面しています。
- 市場の飽和: どのSaaSも似たような機能を提供し始め、差別化が困難に。
- 顧客獲得コスト(CAC)の上昇: 広告費や営業コストが高騰し、従来のような高い利益率を確保しづらくなっています。
かつてSaaSモデルの基本理念であった「顧客を一度獲得すれば長期的な収益を得られる(無限のLTV)」という幻想は、現実の厳しい競争環境によって崩れつつあります [2]。
1-2. AIエージェントの台頭:従来のSaaSモデルへの挑戦
「SaaS 時代 終わり」論の最大の引き金は、生成AI、特にAIエージェントの急速な進化です。
AIエージェントは、人間からの指示(例:「経費精算をして」)を受け、複数のシステムを横断して自律的にタスクを完了させる能力を持ちます。
従来のSaaSが「特定の業務を効率化するツール」であったのに対し、AIエージェントは「業務全体を自動で遂行する代理人」です。もしAIエージェントが経費精算、顧客対応、レポート作成といった業務を完全に代替できるなら、特定の機能に特化したSaaSは不要になるのではないか、という危機感がこの議論の核心です。
2. SaaS限界論の核心:グローバルビジネスパーソンが直面する課題
2-1. 経費精算SaaS企業が「AIエージェント企業」へ転換した理由
この危機感を最も強く表明したのが、日本の急成長SaaS企業であるTOKIUM(経費精算SaaSを提供)です。同社の社長は、従来のSaaSモデルから「経理AIエージェント企業」への転換を宣言しました [3]。
彼らの「SaaS限界論」の核心は、技術進歩がもたらした皮肉にあります。SaaS開発の難度が下がり、機能が均質化した結果、ユーザーは「どのSaaSを使っても大差ない」と感じるようになり、価格競争に陥りやすくなったのです。
2-2. グローバル企業特有の「SaaSの壁」
この議論は、グローバルビジネスの現場で働く私たちにとって、より切実な問題を含んでいます。
駐在員として海外で働いていると、SaaS導入の際に「グローバル企業特有の壁」に直面します。
(駐在員の視点)
私は現在、アジア某国で事業開発を担当していますが、本社で導入された最新のSaaSが、現地の法令や税制に対応できず、結局、ローカルの古いシステムと二重運用になっているケースを何度も見てきました。
特に、GDPR(EU一般データ保護規則)や各国のインボイス制度など、法令遵守(コンプライアンス)の要件は国によって全く異なります。本社主導で「このSaaSで統一!」となっても、現地の法務・経理部門から「待った」がかかるのは日常茶飯事です。
また、駐在任期や各社の業界・立場によって、SaaS導入の意思決定や予算感が異なるのも現実です。短期的なコスト削減を重視するのか、長期的なグローバル統一基盤を重視するのか、この判断が非常に難しいのです。
AIエージェントが業務を自動化できたとしても、この「法令・監査対応」という、国境をまたぐ複雑な要件を100%満たすには、信頼できる強固な業務基盤が必要不可欠なのです。
3. 「SaaSは死なない」存続派の論理と進化の方向性
3-1. SaaSが担う「信頼性」「監査性」「法令遵守」の重要性
「SaaS is Dead」論に対し、SaaS存続派は強く反論しています。彼らが強調するのは、SaaSが提供する「業務の基盤」としての価値です [4]。
業務で扱うデータは、95%が正しく、5%が誤っているという状態は許されません。特に経理や人事といったバックオフィス業務では、100%の正確性と安定運用が求められます。
SaaSは、この「信頼性」「監査性」「法令遵守」を担保するために設計されています。
- データの正確性: 厳格なデータ検証と整合性の確保。
- アクセス制御: 機密性の高い情報へのアクセス権限を厳密に管理。
- 監査対応: 業務プロセスとデータの履歴を記録し、法的な監査に対応。
AIエージェントは「自律的」であるがゆえに、その動作がブラックボックス化しやすく、上記の要件を完全に満たすのは容易ではありません。SaaSは、AIが安心して業務を遂行するための「土台」として、今後も不可欠なのです。
3-2. AIとの共存モデル:組み込み型AIとハブ型AI
SaaSの未来は、AIエージェントとの「共存」にあります。この共存には、主に二つのモデルが考えられています。
| モデル | 特徴 | 具体例 | 現状の普及度 |
|---|---|---|---|
| 組み込み型AI | SaaS内にAI機能を統合し、特定のタスクを効率化する。SaaSが主役。 | 経費精算SaaSがレシート画像を読み取り、勘定科目を自動入力する。メールSaaSが返信文案を自動生成する。 | 普及段階 |
| ハブ型AI | AIエージェントがユーザーの指示を受け、複数のSaaSを呼び出して業務を完結させる。AIエージェントが主役。 | 「出張の経費精算をして」という指示で、AIが予約SaaS、経費SaaS、会計SaaSを操作し、結果だけをユーザーに返す。 | 将来的なモデル |
現状の「現実解」は、SaaSを基盤としつつ、AIの「得意なこと」(データ処理、画像認識、文章生成など)をSaaS内に組み込む組み込み型AIです。これにより、SaaSはより賢く、より使いやすくなります。
4. AI時代に選ぶべき「次世代SaaS」の条件と戦略
4-1. 従来のSaaSと次世代SaaSの比較
AI時代において、私たちが選ぶべきSaaSは、従来のSaaSとは異なる特徴を持っています。
| 比較項目 | 従来のSaaS | 次世代SaaS |
|---|---|---|
| 機能の焦点 | 特定業務の効率化(ツール) | 業務プロセス全体の自動化(基盤+AI) |
| AIとの関係 | AI機能は限定的、または外部連携 | 組み込み型AIが標準搭載、ハブ型AIとの連携を前提 |
| 市場戦略 | 水平展開(幅広い業種・業務に対応) | 垂直展開(特定業界・業務に深く特化) |
| 価格モデル | ユーザー数ベースの月額課金 | 価値ベース/利用ベースの柔軟な課金モデル |
| グローバル対応 | ローカライズは限定的 | 各国の法令・監査要件への対応を重視 |
4-2. 次世代SaaSの3つの特徴
次世代SaaSを選ぶ上で、特に注目すべき3つの特徴があります。
- 特定業界に特化したバーティカルSaaS:
水平型SaaS(幅広い業種に提供)が飽和する中、医療、建設、金融など、特定の業界の深い課題に特化したバーティカルSaaSが成長しています。業界特有の複雑な法令や商習慣に対応できる点が、グローバル企業にとって大きな魅力となります。 - 柔軟な価値ベースの価格モデルへの変化:
ユーザー数ではなく、「処理したトランザクション数」や「削減できた工数」など、提供価値に基づいた価格モデルへの移行が進んでいます。これにより、SaaSの費用対効果がより明確になります。 - AIエージェントとの連携を前提としたAPI公開:
将来的なハブ型AIの時代を見据え、自社のSaaSをAIエージェントが容易に操作できるよう、API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)を積極的に公開しているSaaSが有利になります。
4-3. 駐在員・グローバルビジネスパーソンが取るべき戦略
「SaaS 時代 終わり」という議論は、私たちに「SaaSは道具である」という原点に立ち返る機会を与えてくれました。
AI時代を生き抜くための戦略は、AIとSaaSを組み合わせた最適な業務フローを設計することに尽きます。
- AIに任せる部分の明確化: AIエージェントに任せられる「自律的なタスク」(データ入力、単純な判断)を切り出す。
- SaaSに任せる部分の厳選: 「信頼性」「法令遵守」「監査性」が求められる「業務基盤」を担うSaaSを厳選する。
- 連携を前提としたツール選定: 組み込み型AIが充実しているか、将来的にハブ型AIと連携しやすいAPIを持っているかを判断基準にする。
まとめ:SaaSは「進化」した。あなたのDX戦略を再構築せよ
「SaaSの時代は終わったか?」という問いに対し、私たちの答えは「従来のSaaSの時代は終わり、AIと共存する次世代SaaSの時代が始まった」です。
SaaSは、AIとの共存を通じて、より信頼性の高い「業務基盤」へと進化しました。
AI時代を生き抜くための重要なポイントは、以下の3点です。
- 信頼性: 業務基盤としての100%の正確性を担保できるか。
- 法令遵守: グローバルな法令・監査要件に対応できるか。
- AI統合: AIエージェントとの連携を前提とした進化を遂げているか。
今すぐ、あなたの会社のSaaSポートフォリオを見直し、AI時代に対応したDX戦略を再構築しましょう。この変革の波を乗りこなし、グローバルビジネスの最前線で、より豊かな生活とキャリアを築いていくための第一歩となるはずです。
この記事を読んで、あなたの会社のSaaS戦略に疑問を感じた方は、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。また、この記事があなたのDX戦略のヒントになったなら、SNSでシェアしていただけると幸いです。
引用元
[1] アメリカを中心に広がった議論「SaaS is Dead」論とは何か? | SaaS Career Lab | カノープス株式会社 (https://cano-pus.com/lab/2025/01/10/trend-saasisdead-001/)
[2] SaaS is Dead?2025年に見えてきた新たな市場動向と可能性 | FIDX (https://www.fidx.co.jp/saas-is-dead%EF%BC%9F2025%E5%B9%B4%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%8B%95%E5%90%91%E3%81%A8%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7/)
[3] 「SaaSはもう限界」 急成長SaaSが、AIエージェント企業に大転換──その“深刻な危機感”(1/2 ページ) – ITmedia ビジネスオンライン (https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2507/17/news017.html)
[4] SaaSは死なない。人と共存する ラクスがSaaS is Deadに反論 – Impress Watch (https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/2056770.html)

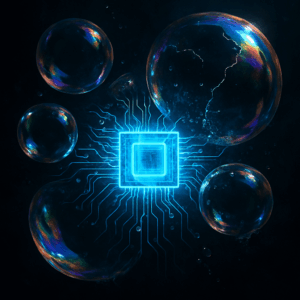
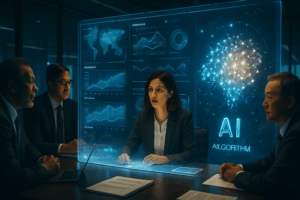
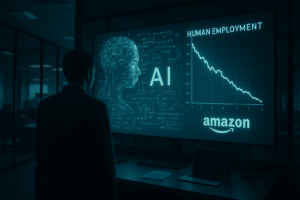
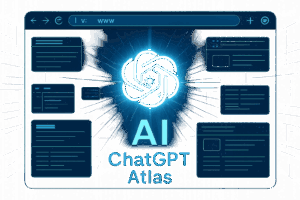
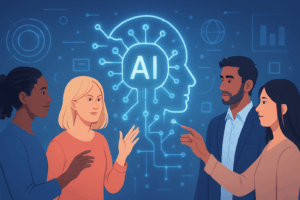
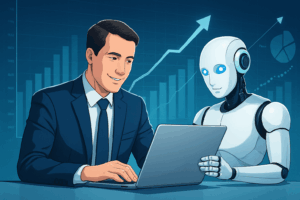
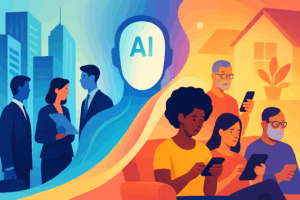
コメント