はじめに:不確実な時代を生き抜く駐在員家族へ
「2025年、2026年のヨーロッパ経済はどうなるんだろう?」
海外で生活する駐在員の皆さん、特に小さなお子さんを育てながら異国の地で奮闘されている方々は、常に未来への漠然とした不安を抱えているのではないでしょうか。経済の動向は、私たちのビジネス、家計、そして何よりも大切な子供たちの教育や将来に直結します。特に、近年は米国関税の動向、中東やウクライナ情勢に代表される地政学的リスク、そしてインフレや金利変動といった経済の不確実性が高まり、その影響はヨーロッパに暮らす駐在員家族にとって決して無視できないものとなっています。
「この経済状況で、子供の教育はどうすればいい?」「せっかくの海外生活、資産運用はどう見直すべき?」
そんな疑問や悩みを抱えるのは当然のことです。しかし、ご安心ください。本記事では、KPMG、JRI、IMF、JETROといった信頼できる機関の最新データを基に、2025年から2026年にかけてのヨーロッパ経済見通しを徹底的に解説します。そして、その経済状況が駐在員家族の皆さんの生活にどのような影響を与えるのかを具体的に考察し、豊かな未来を築くための実践的な対策と戦略を分かりやすくお伝えします。
この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が解消され、具体的な行動指針が見えてくるはずです。家族の未来を守るための知識を身につけ、賢い選択をするための第一歩を踏み出しましょう。
目次
- 【最新データ】2025-2026年ヨーロッパ経済の全体像と主要トレンド
- 米国関税と地政学的リスク:駐在員のビジネス環境への影響
- 駐在員家庭の家計を守る!インフレ・金利変動と資産運用戦略
- 子供の未来と教育:経済変動下での駐在員家庭の選択肢
- 駐在員のキャリアと生活:多様な視点と柔軟な対応
- まとめ:不確実な時代を生き抜く駐在員家族の未来戦略
1. 【最新データ】2025-2026年ヨーロッパ経済の全体像と主要トレンド
2025年から2026年にかけてのヨーロッパ経済は、緩やかな回復基調にあるものの、複数の不確実要因を抱えながら推移すると予測されています。主要な経済機関の発表を総合すると、ユーロ圏のGDP成長率は限定的ながらもプラスを維持し、インフレ率はECBの目標値に近づく見込みです。
主要経済機関の予測比較
以下に、KPMG、JRI、IMF、JETROといった主要機関が発表している2025年および2026年のユーロ圏経済見通しをまとめました。各機関で若干の差異はありますが、全体的な傾向としては緩やかな成長が予測されています。
| 機関名 | 項目 | 2025年予測 | 2026年予測 |
|---|---|---|---|
| KPMG | ユーロ圏GDP成長率 | 約0.9% | – |
| JRI | ユーロ圏GDP成長率 | 約0.9% | 約1.4% |
| IMF | ユーロ圏GDP成長率 | 1.0% | 1.2% |
| JETRO | EU実質GDP成長率 | 1.1% | 1.5% |
*注:各機関の発表時期や対象範囲(ユーロ圏かEU全体か)により数値に差異があります。
これらの予測から、ユーロ圏のGDP成長率は2025年に0.9%~1.1%、2026年には1.2%~1.5%程度と見込まれています。特にIMFは、アイルランドの好調なGDPがユーロ圏全体の成長率を押し上げていると指摘しており、アイルランドを除いたユーロ圏の成長率は0.1%ポイントの上方修正にとどまると分析しています。これは、アイルランドの新しい生産施設の開設による医薬品輸出の大幅な増加が背景にあるとのことです。
インフレ率と金融政策の動向
インフレ率に関しては、各機関ともに2025年には2.2%程度、2026年には2.1%程度と、欧州中央銀行(ECB)の目標である2.0%付近で安定すると予測しています。実質賃金の上昇も期待されており、これが個人消費を堅調に支える主要因となるでしょう。
ECBは、インフレ抑制のために実施してきた利上げサイクルを終え、2025年後半には0.25%の利下げを実施する可能性が高いと見られています。その後は金利を据え置くとの見方が有力です。一方、イングランド銀行(BOE)は、インフレ動向を見極めながらも、半年に1回のペースで利下げを行い、年末までに政策金利が4%へ低下する見通しです。これらの金融政策の動向は、駐在員の住宅ローンや資産運用に直接的な影響を与えるため、今後の発表には注意が必要です。
経済を左右する主要因
ヨーロッパ経済の動向を左右する主要因としては、以下の点が挙げられます。
- 個人消費の回復: 実質賃金の上昇とインフレの鈍化により、個人消費は堅調に推移すると見られています。特にスペイン経済の好調さがユーロ圏全体の消費を下支えするでしょう。
- 企業の投資活動: ECBの利下げにより、企業の投資活動が回復し、総資本形成の増加が予測されています。
- 米国の貿易政策: 米国による追加関税措置は、EUにとって最大の貿易相手国である米国との貿易関係に大きな影響を与え、特にドイツ、アイルランド、オランダ、フランスからの輸出に打撃を与える可能性があります。これにより、EU企業は代替市場の開拓を迫られるかもしれません。
- 地政学的リスク: 中東やウクライナ情勢の緊迫化は、エネルギー価格の変動やサプライチェーンの混乱を引き起こし、経済成長の足かせとなる可能性があります。
- 財政政策: ドイツの財政拡張やユーロ圏全体の防衛費増額は、短期的に景気を押し上げる要因となる一方で、公的債務の増加という課題も抱えています。
駐在員の皆さんにとっては、これらのマクロ経済の動向を理解することが、自身のビジネスや家族の生活設計を考える上で不可欠です。次のセクションでは、特に駐在員のビジネス環境に大きな影響を与える「米国関税と地政学的リスク」について深く掘り下げていきます。
2. 米国関税と地政学的リスク:駐在員のビジネス環境への影響
ヨーロッパ経済の未来を語る上で、米国関税の動向と地政学的リスクは避けて通れない重要なテーマです。これらは、駐在員の皆さんのビジネス環境に直接的かつ深刻な影響を及ぼす可能性があります。
米国関税がもたらすビジネスへの影響
米国はEUにとって最大の貿易相手国であり、その貿易政策は欧州経済に大きな影響を与えます。特に、米国が追加関税措置を講じた場合、ドイツ、アイルランド、オランダ、フランスといった主要国からの機械・輸送機器、化学品、医薬品、高級消費財の輸出が大きな打撃を受けるとJETROは指摘しています。IMFの報告書でも、実効関税率の再上昇が世界経済の成長鈍化につながる可能性が示唆されており、この不確実性が企業活動の重荷となることが懸念されています。
駐在員が直面する可能性のある課題:
- サプライチェーンの混乱と再編: 関税の影響で部品調達コストが増加したり、既存のサプライチェーンが寸断されたりする可能性があります。企業は代替供給源の確保や生産拠点の見直しを迫られ、駐在員は新たなサプライヤーとの交渉や物流ルートの再構築といった業務に追われるかもしれません。
- 企業戦略の変更と市場開拓の圧力: 米国市場での競争力が低下すれば、企業は東南アジアや中南米、アフリカといった代替市場への輸出強化を検討するでしょう。しかし、これらの市場は利益率が低く、異なる規制への対応コストも発生するため、駐在員には新たな市場での厳しい競争と、それに伴う戦略立案・実行が求められます。
- M&A動向の変化: 貿易摩擦の激化は、企業のM&A戦略にも影響を与えます。競争力強化のための業界再編や、リスク分散のための事業売却などが活発化する可能性があり、駐在員はこれらの動きに迅速に対応し、自社の事業を有利に進めるための交渉力や分析力が一層重要になります。
地政学的リスクの影
中東情勢の緊迫化やウクライナ紛争の長期化といった地政学的リスクは、エネルギー価格の変動や物流コストの上昇を通じて、欧州経済全体に負の影響を与え続けています。IMFは、地政学的緊張によって世界のサプライチェーンが混乱し、一次産品価格が上がる可能性を指摘しています。
駐在員のビジネスと生活への影響:
- エネルギーコストの増加: 原油価格の高騰は、製造業の生産コストや輸送コストを押し上げ、企業の収益を圧迫します。駐在員の皆さんの生活においても、電気代やガソリン代の上昇という形で家計に影響を及ぼすでしょう。
- 市場の不確実性: 地政学的リスクは投資家の心理を冷え込ませ、市場のボラティリティを高めます。これにより、企業の投資計画が遅延したり、新規事業の立ち上げが見送られたりする可能性があります。駐在員は、このような不確実性の高い環境下で、常に最新の情報を収集し、リスクを評価しながらビジネスを進める必要があります。
- 駐在員生活への影響: 紛争地域に近い国や、エネルギー供給を依存している国では、生活物資の不足や治安の悪化といった間接的な影響も懸念されます。家族の安全確保や、緊急時の対応計画を事前に立てておくことが重要です。
駐在員の体験談(匿名)
あるドイツ駐在の製造業勤務のAさんは、米国関税の影響で主要部品の調達が困難になった経験を語ってくれました。「これまで安定していたサプライヤーからの供給が滞り、急遽、代替品を探す必要に迫られました。コストは上がりましたが、生産ラインを止めるわけにはいかない。現地スタッフと協力し、数週間かけて新たな調達先を確保しましたが、その間のプレッシャーは相当なものでした。」
また、中東情勢の緊迫化により、物流コストが急騰した経験を持つフランス駐在のBさんは、「海上輸送の保険料が跳ね上がり、納期も不安定になりました。顧客への説明と価格交渉に追われ、精神的に疲弊しました。しかし、こうした状況下でこそ、現地でのネットワークや情報収集の重要性を痛感しました」と話しています。
これらの体験談は、不確実性の高い時代において、駐在員が直面する現実と、それを乗り越えるための知恵を示唆しています。次のセクションでは、このような経済環境下で駐在員家庭がどのように家計を守り、資産を形成していくべきか、具体的な資産運用戦略について掘り下げていきます。
3. 駐在員家庭の家計を守る!インフレ・金利変動と資産運用戦略
経済の不確実性が高まる中、駐在員家庭にとって家計の安定と資産形成は喫緊の課題です。特に、インフレと金利の変動は、日々の生活費から将来の資産運用まで、あらゆる側面に影響を及ぼします。ここでは、ECBとBOEの金融政策の見通しを踏まえ、駐在員が取るべき具体的な資産運用戦略と家計防衛策を解説します。
金融政策の動向と駐在員への影響
欧州中央銀行(ECB)は、インフレ抑制のために行ってきた利上げサイクルを終え、2025年後半には0.25%の利下げを実施する可能性が高いと見られています。その後は金利を据え置くとの見方が有力です。一方、イングランド銀行(BOE)は、インフレ動向を慎重に見極めながらも、半年に1回のペースで利下げを行い、年末までに政策金利が4%へ低下する見通しです。
これらの金利変動は、駐在員の皆さんの家計に以下のような影響を与えます。
- 住宅ローン: 変動金利型の住宅ローンを組んでいる場合、利下げは月々の返済額を軽減する可能性があります。しかし、固定金利型の場合は影響が限定的です。今後の金利動向を注視し、必要に応じて借り換えや金利タイプの見直しを検討することが重要です。
- 貯蓄・預金: 利下げは預金金利の低下を意味し、銀行預金だけでは資産が増えにくい状況が続くでしょう。インフレ率が預金金利を上回る「実質マイナス金利」の状態では、資産が目減りするリスクもあります。
- 投資: 金利の低下は、株式市場や不動産市場にプラスの影響を与える可能性があります。企業の資金調達コストが下がり、投資が活発化することで、株価の上昇や不動産価格の安定・上昇が期待できます。
高インフレ時代を乗り切る家計防衛策
インフレが続く環境下では、ただ貯蓄するだけでは資産価値が目減りしてしまいます。駐在員家庭が家計を守るために、以下の対策を検討しましょう。
- 家計の見直しと固定費削減: まずは家計の現状を把握し、無駄な支出がないか見直しましょう。特に、住居費、通信費、保険料などの固定費は、一度見直せば継続的な節約効果が期待できます。例えば、より安価な通信プランへの変更や、不要な保険の見直しなどが挙げられます。
- インフレに強い資産への投資: 株式、不動産、金などの実物資産は、インフレに強い傾向があります。特に、成長が見込まれる企業の株式や、賃料収入が期待できる不動産への投資は、インフレヘッジとして有効です。ただし、リスクも伴うため、分散投資を心がけましょう。
- 外貨建て資産の活用: 複数の通貨で資産を持つことは、為替リスクを分散し、特定の通貨の価値下落から資産を守る効果があります。駐在先の通貨だけでなく、米ドルや日本円など、主要通貨での資産保有を検討しましょう。
駐在員のための資産運用戦略
駐在員は、日本と異なる税制や金融制度の中で資産運用を行う必要があります。以下のポイントを踏まえて、賢い資産運用戦略を立てましょう。
- 税制優遇制度の活用: 駐在先の国によっては、非居住者向けの税制優遇制度や、特定の投資に対する税制優遇措置がある場合があります。現地の税理士やファイナンシャルプランナーに相談し、利用可能な制度を最大限に活用しましょう。また、日本に帰国後のNISAやiDeCoといった制度も視野に入れ、長期的な視点で計画を立てることが重要です。
- 国際分散投資の徹底: 特定の国や地域に偏らず、世界中の株式、債券、不動産などに分散投資を行うことで、リスクを低減し、安定したリターンを目指します。特に、先進国だけでなく、成長著しい新興国の市場にも目を向けることで、より高い成長機会を捉えることができます。
- 為替リスクヘッジの検討: 為替変動は、海外資産の価値に大きな影響を与えます。将来的に日本円で資産を使う予定がある場合は、為替ヘッジ付きの金融商品を選ぶ、あるいは定期的に円転するなど、為替リスクを管理する戦略を検討しましょう。特に、Wiseのような海外送金サービスは、低コストで為替リスクを抑えながら資金移動ができるため、積極的に活用することをおすすめします。
駐在員の体験談(匿名)
シンガポール駐在経験のあるCさんは、「海外赴任を機に、日本の銀行預金だけでなく、海外の証券口座を開設し、米ドル建ての投資信託を始めました。為替変動には常に気を配っていますが、円安の恩恵を受けることもあり、結果的に資産を増やすことができました。現地のファイナンシャルプランナーに相談したのが大きかったですね」と語っています。
また、ドイツ駐在のDさんは、「インフレで食費や光熱費が上がった分、サブスクリプションサービスの見直しや、外食を減らすなど、家計の引き締めを徹底しました。同時に、子供の教育資金のために、毎月一定額を自動で投資に回す仕組みを作っています。無理のない範囲で、継続することが大切だと実感しています」と話しています。
これらの体験談からもわかるように、不確実な経済状況下でも、情報収集と計画的な行動によって、駐在員家庭は家計を守り、資産を増やすことが可能です。次のセクションでは、経済変動が子供たちの教育に与える影響と、駐在員家庭が取るべき選択肢について深く掘り下げていきます。
4. 子供の未来と教育:経済変動下での駐在員家庭の選択肢
駐在員家庭にとって、子供の教育は最も重要な関心事の一つです。経済の変動は、インターナショナルスクール、現地校、日本人学校といった学校選択から、将来の進路、さらには教育費の負担にまで影響を及ぼします。このセクションでは、経済変動下で駐在員家庭がどのように子供の未来と教育を守るべきか、具体的な選択肢と対策を考察します。
経済状況が子供の教育に与える影響
- 教育費の増加: インフレの進行は、インターナショナルスクールの学費や教材費、習い事の費用など、教育にかかるコストを押し上げます。特に、為替変動の影響も加わるため、日本円で教育費を賄う家庭にとっては、予期せぬ負担増となる可能性があります。
- 学校選択の再検討: 経済的な理由から、学費の高いインターナショナルスクールから、比較的費用を抑えられる現地校や日本人学校への転校を検討する家庭も出てくるかもしれません。また、オンライン教育の活用など、新たな選択肢も視野に入れる必要が出てきます。
- 将来の進路への影響: 経済の不確実性は、子供の将来の進路選択にも影響を与えます。例えば、帰国子女枠での大学進学を考えていた場合でも、経済状況によっては国内進学を優先する、あるいは奨学金制度の活用を真剣に検討するなど、柔軟な対応が求められるでしょう。
駐在員家庭が取るべき教育戦略
- 教育費の計画的な準備: 早期からの教育資金準備が不可欠です。学資保険や積立投資など、長期的な視点で教育費を確保する仕組みを構築しましょう。前述の資産運用戦略と合わせて、インフレに負けない資産形成を目指すことが重要です。
- 多様な学校選択肢の検討: インターナショナルスクールだけでなく、現地の公立学校や日本人学校のメリット・デメリットを比較検討しましょう。学費だけでなく、教育内容、言語環境、将来の進路との接続性などを総合的に判断することが大切です。また、オンライン学習プラットフォームや家庭教師の活用も、教育の質を維持しつつ費用を抑える有効な手段となり得ます。
- 語学力維持・向上のための家庭での取り組み: 経済状況に関わらず、駐在生活で得られる最大の財産の一つは語学力です。家庭内で多言語に触れる機会を設けたり、オンライン英会話や現地の語学教室を活用したりするなど、子供の語学力維持・向上に努めましょう。これは、将来のキャリアパスにおいても大きな強みとなります。
- 海外生活への適応を促す心理的サポート: 経済変動による家庭内の不安は、子供にも伝わります。子供が海外生活にスムーズに適応できるよう、積極的にコミュニケーションを取り、不安や悩みに寄り添うことが重要です。現地のコミュニティ活動への参加や、同じ境遇の駐在員家庭との交流も、子供の心の安定に繋がります。
駐在員の体験談(匿名)
フランス駐在のEさんは、円安とインフレの影響でインターナショナルスクールの学費負担が重くなった経験を語ってくれました。「当初はインターナショナルスクールに通わせていましたが、家計への影響が大きくなり、現地校への転校を決めました。子供は最初は戸惑っていましたが、現地の友達ができ、フランス語も飛躍的に上達しました。結果的には、多様な文化に触れる良い機会になったと前向きに捉えています。」
また、ドイツ駐在のFさんは、「子供の帰国後の進路を考え、日本人学校と現地校のどちらにするか悩みました。最終的には、日本語での学習基盤をしっかり築くため日本人学校を選びましたが、放課後や週末には現地のスポーツクラブに参加させ、異文化交流の機会を積極的に作っています。経済状況に左右されず、子供にとって何がベストかを常に考えています」と話しています。
これらの体験談は、経済変動という困難な状況下でも、駐在員家庭が知恵を絞り、子供の未来のために最善の選択をしていることを示しています。重要なのは、変化を恐れず、常に情報を収集し、柔軟に対応する姿勢です。次のセクションでは、駐在員自身のキャリアと生活に焦点を当て、不確実な時代を豊かに生き抜くためのヒントを探ります。
5. 駐在員のキャリアと生活:多様な視点と柔軟な対応
経済の変動は、駐在員自身のキャリアパスや日々の生活にも深く関わってきます。不確実性の高い時代だからこそ、多様な視点を持ち、柔軟に対応する姿勢が駐在員としての成功、そして家族の豊かな生活に繋がります。このセクションでは、経済変動が駐在員のキャリアに与える影響と、充実した駐在員生活を送るためのヒントを探ります。
経済変動が駐在員のキャリアに与える影響
- キャリアパスの再考: 経済の減速や貿易摩擦は、企業の事業戦略に大きな変更をもたらすことがあります。これにより、駐在員の担当業務の変更、赴任期間の短縮・延長、あるいは予期せぬ帰任といった事態が発生する可能性もゼロではありません。常に自身のキャリアパスを見直し、変化に対応できるスキルを身につけることが重要です。
- 求められるスキルの変化: グローバル企業においては、単に現地のビジネスを管理するだけでなく、地政学的リスクの分析、新たな市場の開拓、サプライチェーンの再構築といった、より戦略的な役割が求められるようになります。異文化理解、語学力はもちろんのこと、問題解決能力やリーダーシップ、そして変化への適応力が一層重要視されるでしょう。
- グローバルな視点とネットワークの重要性: 不確実な時代だからこそ、現地の情報だけでなく、グローバルな視点から経済やビジネスの動向を捉える能力が不可欠です。また、現地での人脈形成や、他国の駐在員との情報交換を通じて、多様な視点を取り入れることが、キャリア形成において大きな財産となります。
充実した駐在員生活を送るためのヒント
駐在員生活は、ビジネス面だけでなく、プライベートにおいても多くの挑戦と機会をもたらします。経済変動のストレスに負けず、家族と共に豊かな生活を送るために、以下のヒントを参考にしてください。
- ワークライフバランスの重視: 駐在員は多忙を極めることが多いですが、意識的にワークライフバランスを保つことが重要です。家族との時間、趣味の時間、自己啓発の時間を確保することで、ストレスを軽減し、心身ともに健康な状態を維持できます。ヨーロッパの豊かな文化や自然を積極的に体験し、リフレッシュする機会を作りましょう。
- コミュニティへの積極的な参加: 現地の日本人コミュニティや、多国籍なグループ、趣味のサークルなどに積極的に参加することで、新たな人間関係を築き、精神的な支えを得ることができます。特に、同じ境遇の駐在員家族との交流は、情報交換の場としても、心の拠り所としても非常に有益です。
- 異文化適応とストレス対処法: 異文化環境での生活は、言葉の壁や習慣の違いなど、様々なストレスを伴います。完璧を目指すのではなく、違いを受け入れ、楽しむ姿勢が大切です。また、ストレスを感じた際には、信頼できる人に相談したり、専門のカウンセリングサービスを利用したりすることも有効です。
駐在員の体験談(匿名)
イギリス駐在のGさんは、「経済の先行きが不透明な時期は、会社の業績も厳しくなり、仕事のプレッシャーも増しました。しかし、週末は家族で近郊の自然豊かな場所に出かけたり、現地の友人とフットサルを楽しんだりすることで、うまく気分転換ができています。オンとオフの切り替えが、駐在生活を乗り切る秘訣だと感じています」と語っています。
また、オランダ駐在のHさんは、「赴任当初は現地の文化に馴染めず苦労しましたが、現地の語学学校に通い、積極的にイベントに参加するうちに、多くの友人ができました。彼らとの交流を通じて、多様な価値観に触れることができ、自身の視野も広がったと感じています。経済状況がどうであれ、異文化を楽しむ姿勢が大切ですね」と話しています。
これらの体験談は、経済的な困難に直面しても、駐在員が自身のキャリアと生活を豊かにするためのヒントを与えてくれます。次のセクションでは、本記事のまとめとして、不確実な時代を生き抜く駐在員家族の未来戦略を再確認します。
6. まとめ:不確実な時代を生き抜く駐在員家族の未来戦略
2025年から2026年にかけてのヨーロッパ経済は、緩やかな成長が見込まれる一方で、米国関税の動向、地政学的リスク、インフレ・金利変動といった複数の不確実性を抱えています。しかし、本記事で解説したように、これらの経済状況を正確に理解し、適切な対策を講じることで、駐在員家族は不安を乗り越え、豊かな未来を築くことが可能です。
駐在員家族が未来を切り開くための重要ポイント
- 経済動向の継続的な把握: KPMG、JRI、IMF、JETROなどの信頼できる情報源から、常に最新の経済見通しを収集し、自身のビジネスや家計への影響を分析する習慣をつけましょう。
- 計画的な資産防衛と形成: インフレや為替変動に強い資産運用戦略を立て、税制優遇制度や国際分散投資を積極的に活用しましょう。Wiseのような海外送金サービスも賢く利用し、家計の効率化を図ることが重要です。
- 子供の教育と将来への投資: 経済状況に左右されず、子供にとって最適な教育環境を選択できるよう、早期からの教育資金準備と多様な学校選択肢の検討を進めましょう。語学力維持・向上への取り組みも忘れずに行い、将来の選択肢を広げることが大切です。
- キャリアと生活の柔軟な対応: 経済変動はキャリアパスに影響を与える可能性がありますが、変化を恐れず、新たなスキル習得やネットワーク構築に努めましょう。ワークライフバランスを重視し、コミュニティへの参加や異文化適応を通じて、充実した駐在員生活を送ることが、家族全体の幸福に繋がります。
不確実な時代だからこそ、情報収集力、分析力、そして何よりも「変化に対応する柔軟性」が駐在員家族には求められます。本記事が、皆さんの不安を解消し、具体的な行動への一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
読者の皆さんへ:あなたの経験を教えてください!
この記事を読んで、皆さんがヨーロッパ経済について感じたこと、あるいは駐在員生活で実践している経済対策や家族戦略があれば、ぜひコメントで教えてください。皆さんの貴重な経験が、他の駐在員家族の助けになります。
また、本記事で紹介した資産運用サービスや教育関連情報にご興味があれば、ぜひ詳細をご確認ください。あなたの未来をより豊かにするためのヒントがきっと見つかるはずです。
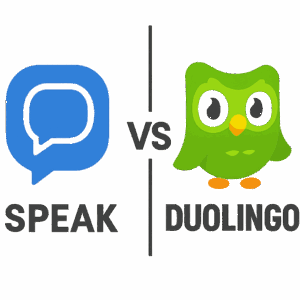

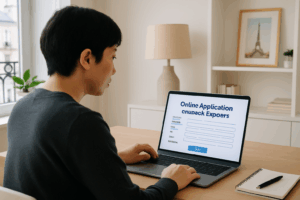





コメント